
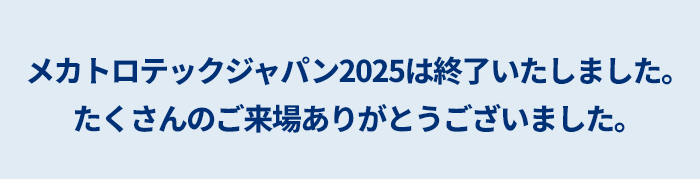

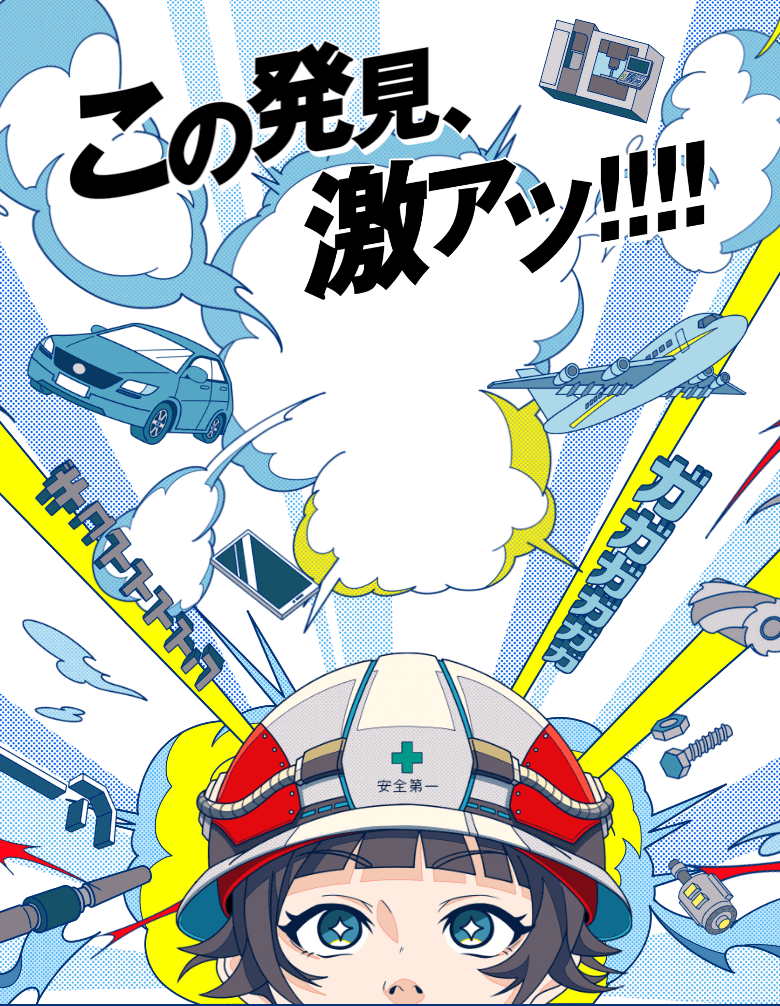

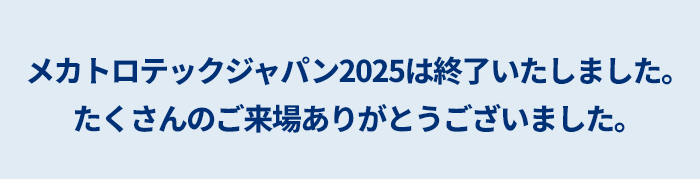

メカトロテックジャパン2025は盛況のうちに終了いたしました。ご来場いただき、誠にありがとうございました。会期中の来場者数は以下の通りです。
4日間合計:77,613人
1日目:18,728人 2日目:21,194人 3日目:23,714人 4日目:13,977人
会期中の来場者数をまとめたPDFデータはこちらからご確認いただけます。
【10月25日(土)来場者数】13,977人/4日間合計:77,613人
【10月24日(金)来場者数】23,714人/3日間合計:63,636人
【10月23日(木)来場者数】21,194人/2日間合計:39,922人
【10月22日(水)来場者数】18,728人
キッチンカーコーディネート事業者募集を締め切りました。
MECT2025公式ウェブサイトを公開しました。

主催者企画展示 /
主催者セミナー
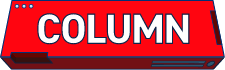
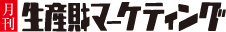
本連載はMECT2025公式メディア「月刊生産財マーケティング」とのコラボ企画です。
MECT2025の出展者情報や恒例の主催者企画展示(コンセプトゾーン)、会期中に開催されるセミナーといった
さまざまな見どころをお届けします。また本連載は月刊生産財マーケティングにも掲載されます。